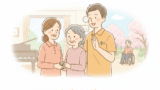日本の認知症対策「認知症施策推進大綱」とは?
「認知症」と聞くと、ご家族の介護や将来への不安を感じる方も多いのではないでしょうか。厚生労働省の推計では、2025年には高齢者の5人に1人(約700万人)が認知症になると言われています。
この深刻な問題に対し、日本政府は2019年に「認知症施策推進大綱」を策定しました。この大綱は、「認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる社会」を目指すための包括的な戦略です。今回は、この大綱の2つの柱である「共生」と「予防」を中心に、知っておくべき国の取り組みをご紹介します。
1. 認知症の「現状と課題」
認知症は単なる物忘れではありません。脳の病気や障害により、日常生活に支障をきたす状態を指します。記憶障害だけでなく、言語能力や判断力の低下、感情のコントロールが難しくなるなど、症状は多岐にわたります。
特に、65歳未満で発症する「若年性認知症」は、働き盛りの世代に影響を与え、本人や家族の生活に大きな負担をかけます。また、徘徊や暴言などの「行動・心理症状(BPSD)」は、24時間対応が必要となり、介護者の精神的・肉体的負担も深刻です。
2. 「共生」と「予防」:二つの柱
「認知症施策推進大綱」は、「共生」と「予防」を車の両輪としています。
- 共生: 認知症の人も、そうでない人も、同じ社会で共に生きるという考え方です。
- 地域住民への理解促進
- 認知症カフェや就労支援
- 「認知症の人にやさしい社会」の実現
- 予防: 認知症の発症を遅らせたり、進行を緩やかにしたりする取り組みです。
- 健康的な生活習慣(食事、運動、睡眠)
- 社会参加や趣味活動の奨励
3. 医療・介護体制と研究開発
国は、早期診断・早期対応を可能にするため、かかりつけ医と専門医療機関の連携を強化しています。また、認知症サポーター養成講座を通じて、地域全体で認知症の人を支える体制づくりを進めています。
さらに、新たな診断法や治療薬の研究開発、ICTやロボット技術の活用も進んでいます。これにより、将来的に認知症をより深く理解し、効果的な治療法を確立することを目指しています。
まとめ
認知症は、誰にとっても無関係ではありません。この動画が示すように、社会全体で認知症を正しく理解し、支え合う仕組みが作られつつあります。私たちがこの問題に「自分事」として関心を持つことが、認知症になっても安心して暮らせる社会を作る第一歩となります。