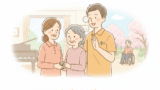認知症ケアの「倫理」:迷った時の羅針盤
認知症ケアの現場では、「転倒を避けるためにベッド柵を設置すべきか、それとも本人の自由な動きを尊重すべきか?」といった、答えを一つに決められない倫理的ジレンマに直面することが多くあります。このような状況で、私たちがどのように考え、判断すべきか。今回は、ケアの質を高めるための倫理的視点と、意思決定支援の重要性について解説します。
1. 倫理的ケアの4つの原則
認知症ケアの指針となるべき倫理的な原則は、主に以下の4つです。
- 自律の尊重: 本人の意思や選択を尊重し、可能な限り自己決定を支援する。
- 無危害: 身体的・精神的な危害を避ける。
- 善行: 本人の利益になるように行動する。
- 正義: 公平性を持ってケアを提供する。
これらの原則は、互いに矛盾することもあります。例えば、「転倒させない(無危害)」という目的と、「自由に歩きたい(自律の尊重)」という本人の希望が対立する場面です。このような時、一方だけを優先するのではなく、本人の状況や価値観を深く理解した上で、最も良いバランス点を探すことが求められます。
2. 倫理的ジレンマへの対処法
倫理的なジレンマに直面した際は、以下のステップを試すことが有効です。
- 状況の把握: 何が問題で、どんな選択肢があるのかを客観的に洗い出す。
- 非言語サインの読み取り: ご本人の表情、行動、声のトーンから「本当の気持ち」を読み取るよう努める。
- チームでの話し合い: 一人で抱え込まず、医師や看護師、他の介護スタッフ、家族などと情報を共有し、意見を交換する。多職種連携が、より良い解決策を見つける鍵となります。
- 選択肢の提示: 本人が理解できる方法で選択肢を提示し、できる限り自分で決めてもらう。
3. 尊厳を守る「意思決定支援」
認知症があっても、その人には「こうしたい」という意思や希望があります。倫理的ケアでは、その思いを尊重する「意思決定支援」が非常に重要です。
- 「できること」に焦点を当てる: できない部分に注目するのではなく、できることに注目し、それを活かせる環境を整えます。
- 選択肢を減らす工夫: 選択肢が多すぎると混乱するため、例えば「赤と青、どちらがいいですか?」のように、シンプルに提示します。
- 本人らしさの尊重: その人が過去に大切にしていた価値観や習慣を尊重し、支援の判断材料とします。
まとめ
認知症ケアにおける倫理は、単なるルールではなく、ケアの質を根本から支える考え方です。 迷った時は「ご本人の尊厳は守られているか?」という問いを心に留めてください。そして、一人で抱え込まず、チームやご家族と協力することが、倫理的ジレンマを乗り越える力になります。